みなさん、こんにちは。
今回の記事では2020年度から実施される大学入学共通テストの数学の特徴やセンター試験との違いなどについてご説明させていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
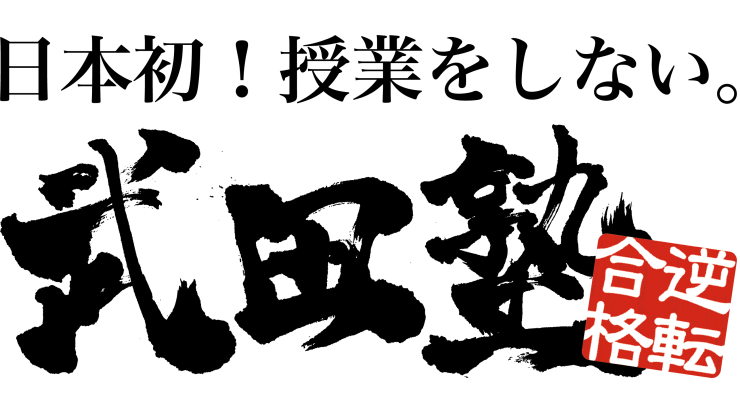
イマからでも間に合う!
難関大学でも武田塾なら逆転合格!
- 授業をしないから『できる』ようになる!
- 自学自習を徹底管理!学習スケジュールをサポート!
- 得意科目と苦手科目を分析した
完全オーダーメイドだから取りこぼしがない!
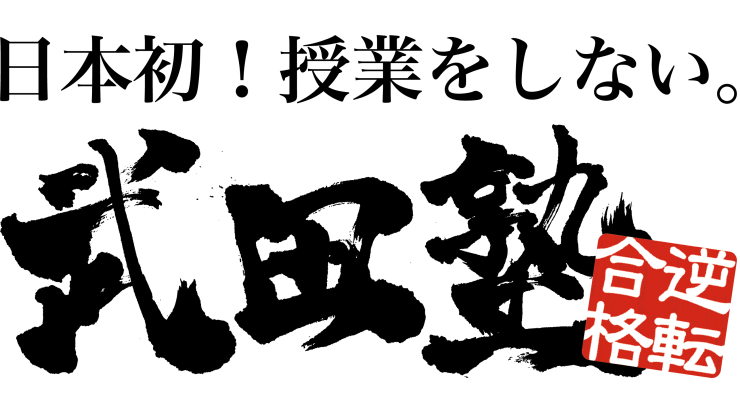
武田塾独自の学習方法で毎年多くの難関大学校合格に導いています。
無料受講相談では、武田塾の学習方法のご紹介から、現在の実力から志望校合格までのカリキュラムを無料でご提案しています。
まずは一度お近くの校舎へご相談ください!
大学入学共通テストではセンター試験にはなかった記述式問題が登場!
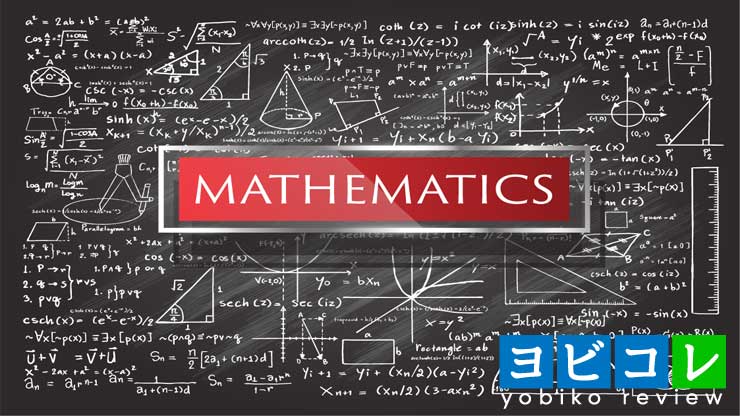
従来国公立大学の2次試験や私立大学のセンター利用入試を受験する場合には毎年1月に行われる「センター試験」を必ず受験する必要がありました。
2020年度入試からはセンター試験に相当する試験が「大学入学共通テスト」へと変わり、問題の特徴や出題形式も大きく変わる予定です。
大学入学共通テストとセンター試験の最大の違いは、記述式の問題があるという点です。
従来のセンター試験では回答をする際には選択肢や計算結果などを指定されたマークシートに鉛筆で記入する形式になっており、記述形式の問題はこれまで1問も登場したことはありませんでした。
しかし、2020年度入試より導入予定の大学入学共通テストでは国語と数学Ⅰ・Aの2科目で記述形式の問題が出題されることになりました。
記述形式の問題が増えた分、数学Ⅰ・Aの試験時間はセンター試験時代と比べると10分間長くなりましたが、再来年以降の受験生は新しい対策をしなければならなくなるでしょう。
どのような記述問題が出題される?
国公立大学の2次試験や私立大学入試などの数学で出題される記述問題は大学によって大きく異なりますが、複雑な途中式をたくさん書いたり、因果関係を詳細に書かなくてはならないものもあります。
平成29年度、および平成30年度に大学入試センターが実施した大学入学共通テストの試行試験の問題を見ると、大学入学共通テストの記述問題はそれほど難易度が高いものではなく、比較的簡単な数式や短めの文章を書かせる問題が多いという特徴があるようです。
難易度の高い記述問題を積極的に解かなくてはならない難関国立大学志望の方であればそれほど苦にはならないでしょうが、マーク式の問題のウェイトが大きい大学を目指している方の場合、日頃から紙と鉛筆を使って手を使いながら数学の問題を解く練習をするなど、記述式問題が出題されることを想定した訓練が求められるでしょう。
より思考力が求められる問題が中心に

従来のセンター試験の数学で出題される問題は難易度が高かった年度をのぞいて単純でワンパターンな問題が多いという特徴があり、数年分の過去問や基本的な問題集などを演習すればそれほど時間をかけずにある程度高い得点を取ることが可能でした。
しかし、大学入学共通テストでは今までのような単純な問題は少なくなり、試験会場でじっくり考えることが要求される問題が増える予想になっています。
また問題文についても複数の生徒が話し合いながらある問いの答えを求めていくという形式になっており文章が長いので、問題において求められていることが何なのか短時間で的確に理解することも重要になります。
このような特徴を持つ問題を確実に解くには教科書や問題集に載っている公式や解き方などを闇雲に暗記するのではなく、基本を徹底的に叩き込むことが大事でしょう。
いくら外見が複雑であるように見えても、教科書や簡単な問題集で学習できる基本的な知識さえあれば難なく正しい答えを導くことができるものばかりです。
青チャートなどに掲載されている問題やその答えをただ暗記するのではなく、どうしてその答えに辿り着くのかを常に考えて勉強をする習慣をつけることが大切です。
数学の出題内容について
大学入学共通テストの数学において出題される内容は現在の学習指導要領のもとではセンター試験と同様であり、数学Ⅰ・A、数学Ⅱ・Bの教科書に掲載されている内容が範囲となっています。
大学入学共通テストではセンター試験と同様に全ての受験生が必ず解かなくてはならない大問と受験生が自由に解くか解かないか選択できる大問が用意されています。
数学Ⅰ・Aでは「整数」、「図形」、「場合の数と確率」の3つの大問から2つを、数学Ⅱ・Bでは「数列」、「ベクトル」、「確率分布と統計的推測」の3つの大問から2つを選択することになっています。
自分の得意不得意を見極めることが大切
数学Ⅰ・Aにおいて出題される記述式の問題は必ず解かなくてはならない大問の中に含まれているので、どの大問を選択しても記述式の問題を避けることはできません。
選択形式の大問では自分が得意としているものを選ぶことによって点数を高めたり、回答するまでの時間を短縮することができるので、自分の現時点での実力を模擬試験などで測ったうえで本番の試験でどの大問を選ぶのが良いか、よく考えておく必要があるでしょう。
大学入学共通テスト数学の対策方法について
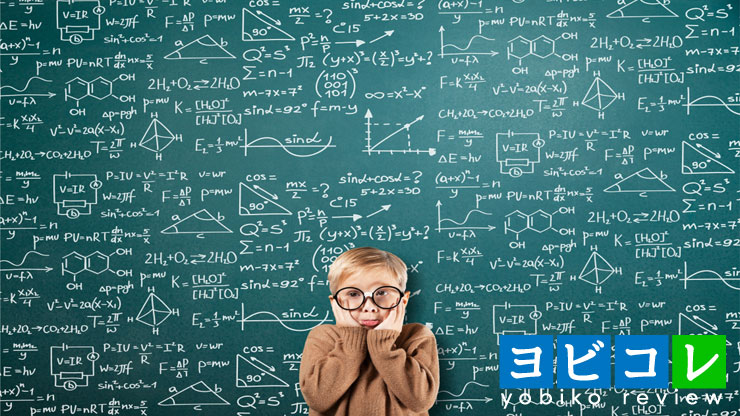
センター試験と異なる点がいくつかあることをお伝えいたしましたが、大学入学共通テストではどのような対策をすべきなのでしょうか。
センター試験の過去問は有効?
これまでに実施されたセンター試験の過去問を大学入学共通テストの練習として使うことはある程度有効であると思われます。
大学入学共通テストはセンター試験と比べ問題形式が大きく異なっていますが、どちらの試験も数学の基本的な知識や技能を要求している点では共通しています。
しっかりと内容を理解できているのか確かめるためにセンター試験の過去問を使うのはそれほど悪い選択肢ではありませんし、マークシートを上手に塗る練習にもなります。
しかし、試験本番直前は大学入学共通テストの形式にあらかじめ慣れておく必要があるので、大学入学共通テストの形式を考慮した問題集を使うことが大事になります。
また駿台や河合塾などの大手予備校が定期的に大学入学共通テストの模擬試験を行っているので、積極的に受験して自分の実力や改善点を洗い出すようにしてください。
今回の記事のまとめ
大学入学共通テストはセンター試験にはなかった記述式の問題が登場したり、以前よりも思考力を問う問題が増えるなど難易度が高くなるという印象が強いですが、教科書や問題集などを使って基本的な内容を完璧に理解すれば、誰でも安定して得点を取ることができるようになるでしょう。

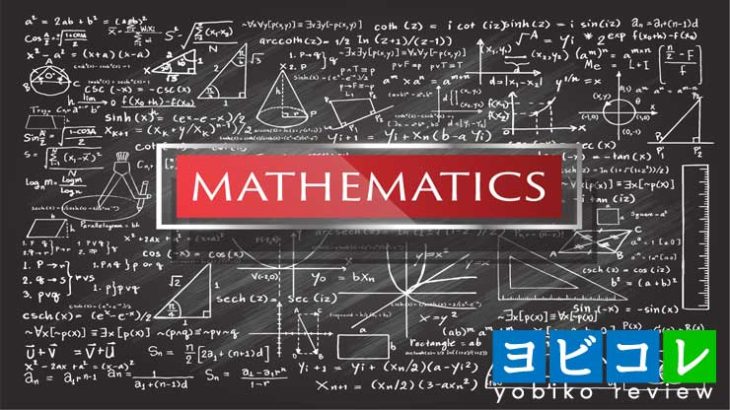






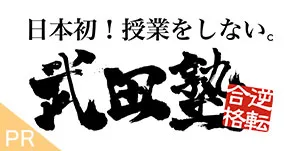
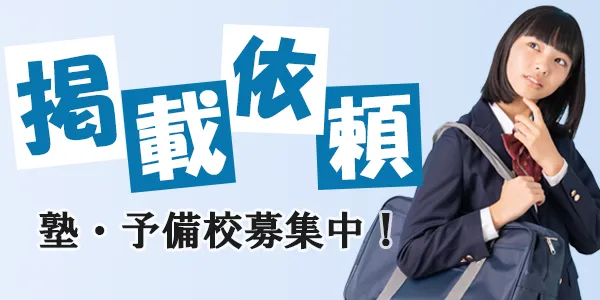
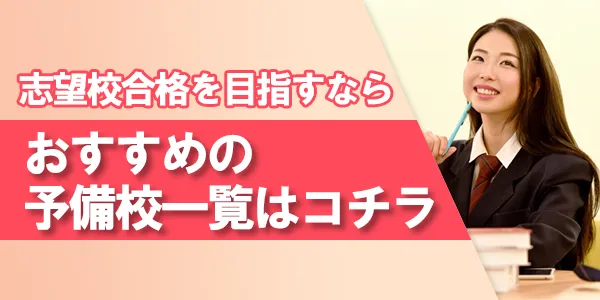
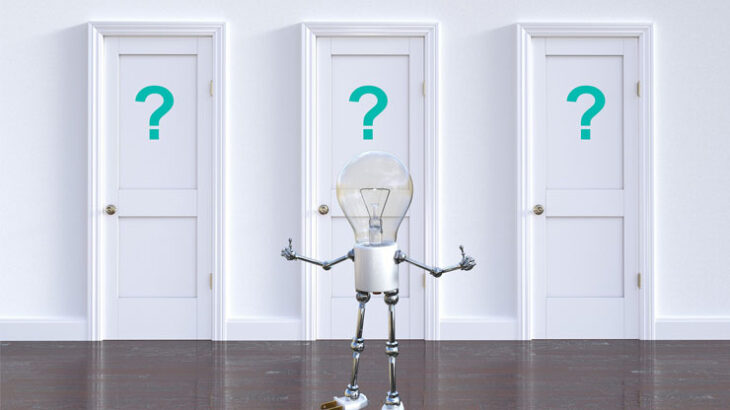

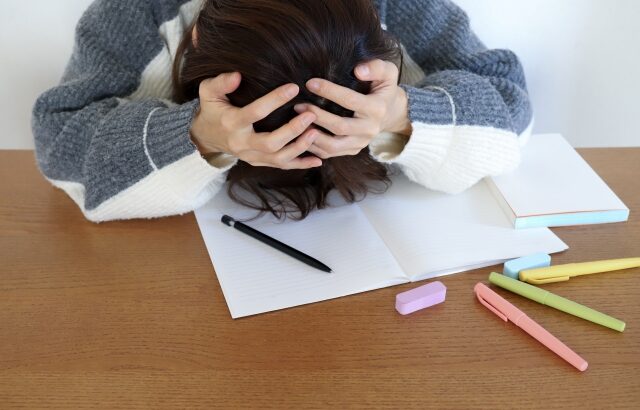


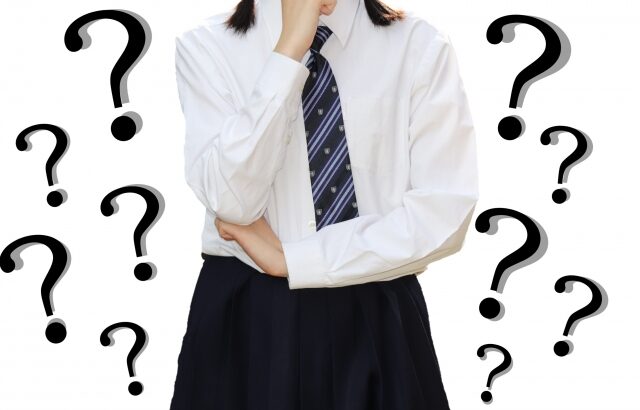
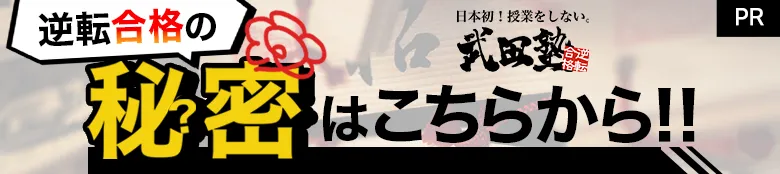
コメントを書く