みなさん、こんにちは。
今回の記事では、2020年度入試より新しく導入される大学入学共通テストは国立大と私立大を受験する場合で数学の記述式問題の割合が異なるのかどうかを中心にご説明させていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
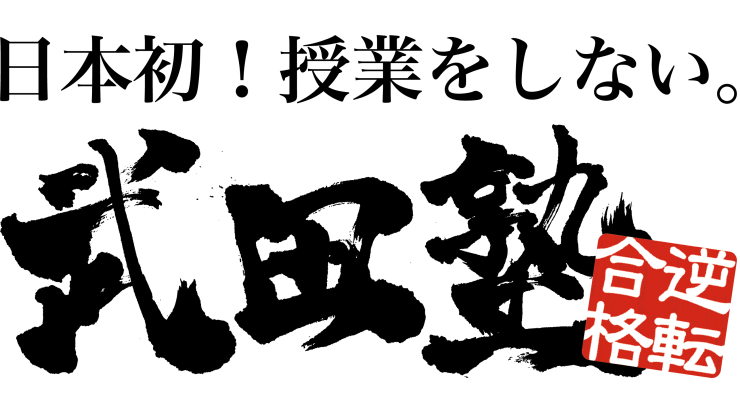
イマからでも間に合う!
難関大学でも武田塾なら逆転合格!
- 授業をしないから『できる』ようになる!
- 自学自習を徹底管理!学習スケジュールをサポート!
- 得意科目と苦手科目を分析した
完全オーダーメイドだから取りこぼしがない!
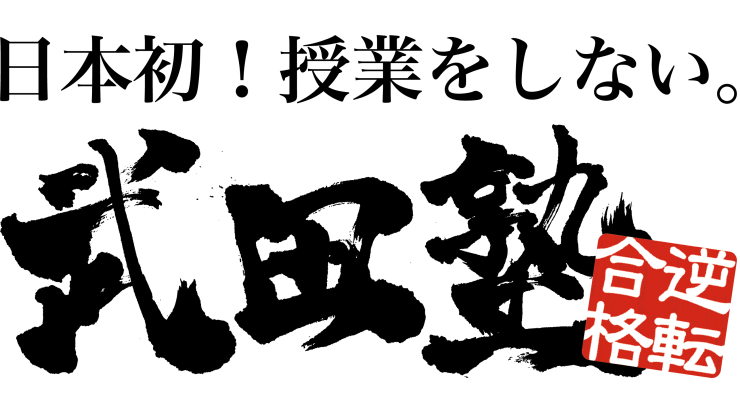
武田塾独自の学習方法で毎年多くの難関大学校合格に導いています。
無料受講相談では、武田塾の学習方法のご紹介から、現在の実力から志望校合格までのカリキュラムを無料でご提案しています。
まずは一度お近くの校舎へご相談ください!
大学入学共通テストで新たに生まれる「記述式問題」

2020年度入試から登場する大学入学共通テストはこれまで数十年間行われていた大学入試センター試験と同じような性質の試験であり、国公立大学を志望している受験生であれば必ず受験する必要があります。
大学入学共通テストでは「国語」と「数学Ⅰ・A」の2科目で記述式の問題が導入されることが発表されています。
国公立大学を受験する方の場合は記述式問題の導入によって確実に影響を受けることになりますが、私立大学のみを志望している受験生にはどのような影響があるのでしょうか。
国立大学を受験する場合と私立大学のみを受験する場合に分けてご説明したいと思います。
国立大学を受験する場合
今までは国立大学の2次試験を受験するためには毎年1月に実施される大学入試センター試験を受験する必要がありました。
東京大学を始めとするいくつかの大学ではセンター試験の点数によっていわゆる「足切り」が行われており、センター試験である一定以上の点数を獲得できた受験生だけが2次試験を受験できるというシステムが存在しています。
2020年度入試以降登場する登場する大学入学共通テストはセンター試験に取って代わられる形で誕生するので、2019年度以前の入試と同様に国立大学を受験したいと考えている受験生は皆大学入学共通テストを受験しなければならなくなるでしょう。
数学は合否に関係する?
東京大学、京都大学、大阪大学などの旧帝国大学を始めとする多くの国立大学は大学入試センター試験の「国語」、「数学」、「英語(筆記とリスニング)」、「地歴公民(理系の学生は理科系科目)」の点数と2月下旬に行われる2次試験の点数が合否判定に使われることになっています。
大学入学共通テストが導入されて以降についてはまだ公式の情報が少なく不確かな部分もありますが、おそらく大学入学共通テストの点数と2次試験の点数が国立大学入試の合否判定に利用されることになるのではいかと思われます。
先ほど述べたように大学入学共通テストの国語と数学Ⅰ・Aでは記述式問題が登場するので、国立大学を受験する場合は基本的には記述式問題を避けることはできないということになります。
大学によっては数学の記述式問題に悩まされることを防げる?
しかし、現時点センター試験で数学を受験しなくても合格が可能である国立大学もわずかながら存在しています。
受験科目に変化がなければ大学入学共通テスト登場以後も大学を選ばなければ数学の記述式問題を避けて国立大学に合格できる可能性はあるでしょう。
私立大学を受験する場合

私立大学は指定校推薦やAO入試など特別な形態のものを除くと、受験の形式は「一般入試」、「センター利用入試」の2つに大きく分けることができます。
一般入試の場合
一般入試とは、各大学が作った入試問題を解き、その結果に基づいて合格者が選ばれる形式で、主に2月に実施されます。
私立大学を受ける場合には多くの人がこの形式の入試に挑戦することになるでしょう。
センター試験時代では一般入試の場合受験生はセンター試験を受験する必要はなく、本番の入試で獲得した点数だけが合否判定に関係していました。
大学入学共通テスト導入以降についても私立大学の一般入試を受験する場合はセンター試験時代と同様に共通テストの結果は合否には関係なく、本番の試験でどれだけ点数を取ることができるのかが重要になります。
したがって、私立大学専願の受験生であれば大学入学共通テストを受験する必要は基本的にはなく、数学の記述式問題を回避することができそうです。
ただし、上智大学や青山学院大学など、共通テストを受験した受験生以外は出願できない入試形式を導入している大学もあるので、自分の志望大学にはどのような受験方法があるのかしっかりと確認しておく必要があるでしょう。
また一部の大学では大学入学共通テストと同時期に登場する「英語民間試験」を合否判定に利用する大学もあるので、注意が必要です。
センター利用入試(共通テスト利用入試)を受験する場合
私立大学の中には大学入試センターの結果だけを使って受験することができるという入試形態(センター利用入試)を採用している大学があります。
センター利用入試は実際に大学に出向くことなく受験することができる方式です。したがって国立大学を第一志望としている受験生にとって受験コストの節約になるので、国立大学の2次試験本番に向けて勉強に集中することができる非常にありがたい制度です。
センター試験が廃止となり、大学入学共通テストが登場してからも共通テストの結果だけを使って受験ができる方式は存続すると見られていますが、早稲田大学を始めとする一部大学では共通テスト利用入試で受験できる学部が減ることが既に宣告されており、選択肢が減ってしまうことが懸念されます。
共通テスト利用入試で必要となる科目は大学によって異なりますが、早稲田大学、明治大学、中央大学などの難易度が比較的高い有名私立大学の場合どの学部でも国語や数学、英語などの主要科目を受験科目に指定する可能性が高いでしょう。
したがって共通テスト利用入試を使って私大合格を狙いたい受験生は数学Ⅰ・Aの記述式問題を避けることはできず、しっかりと対策する必要があるでしょう。
今回の記事のまとめ
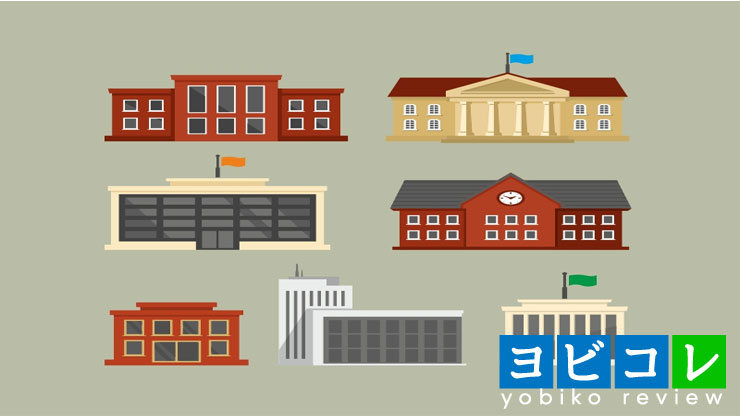
大学入学共通テストにおける記述式問題は国立と私立では異なっており、国立を受ける場合は記述式問題は必須であり、私立大一般入試の場合は大学入学共通テストに関係なく受験ができますが、私立大でも共通テスト利用入試(旧センター利用入試)を活用する場合は国立大と同じく記述式問題を避けることができないということをお伝えいたしました。
自分の志望大学の入試形態を大学のホームページなどでよく確認して、どのような対策をすべきなのか明確にすることが大切でしょう。








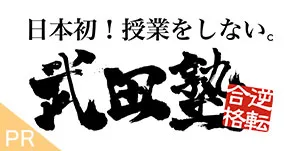
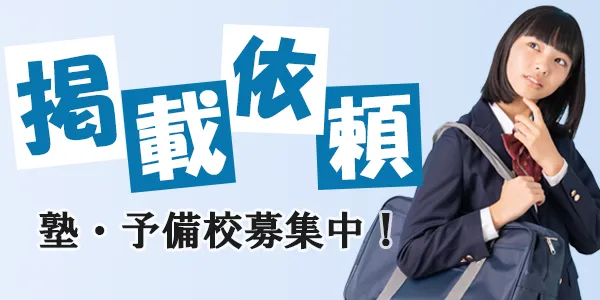
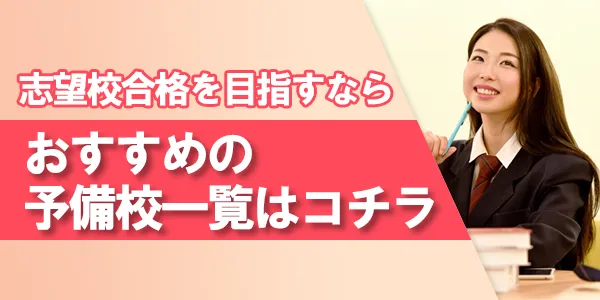
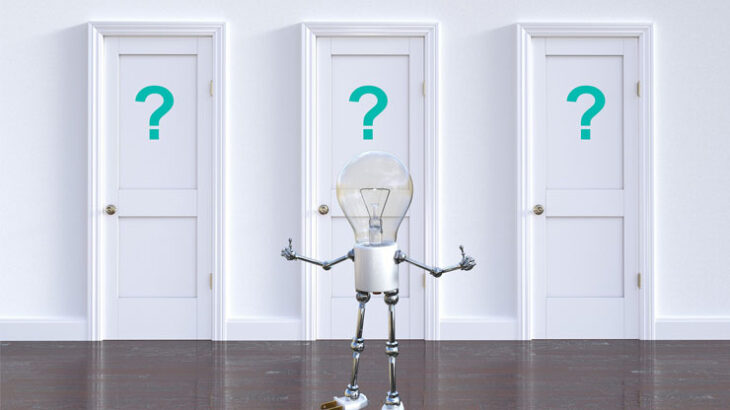

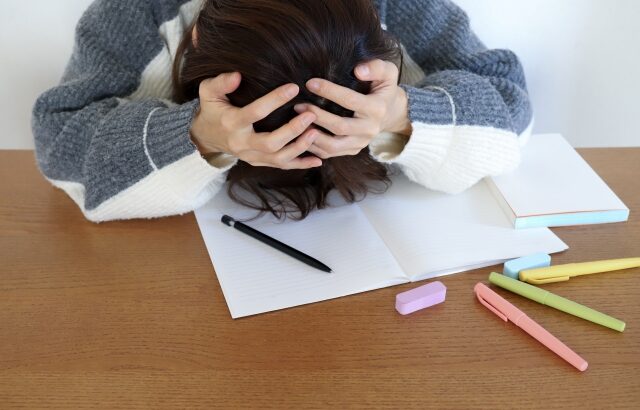


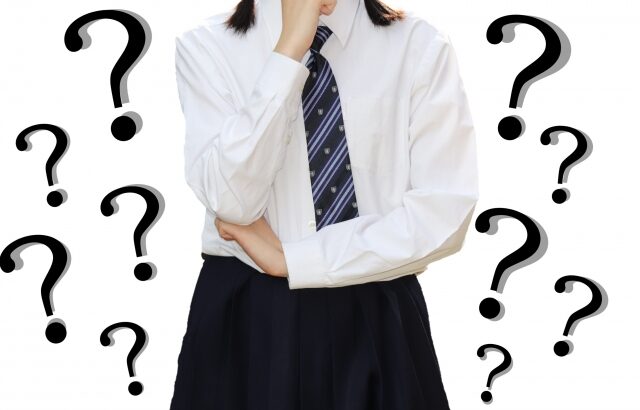
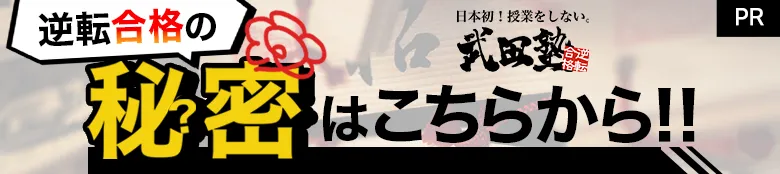
コメントを書く