熊本大学は九州地方の南部に位置する総合大学です。
その医学部は国公立大学の中では中堅から下位クラスの偏差値となっており、九州地方を中心に全国から学生が集まる学部となっています。
その実態はどのようなものなのでしょうか。
今回は、熊本大学医学部の概要と、熊本大学に特徴的な2つの事項を取り上げて、その評判などを分析していきます。
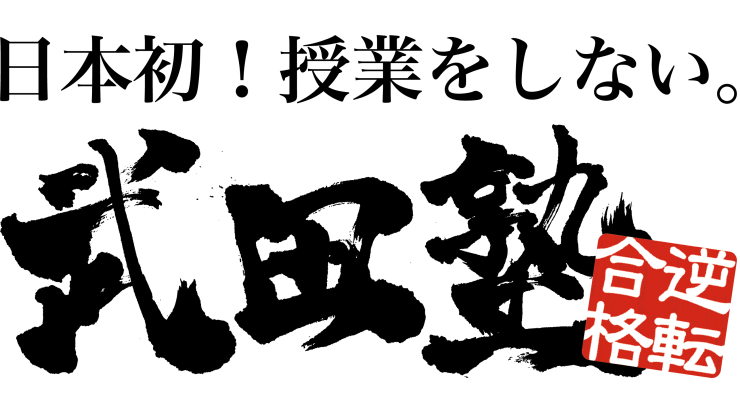
イマからでも間に合う!
難関大学でも武田塾なら逆転合格!
- 授業をしないから『できる』ようになる!
- 自学自習を徹底管理!学習スケジュールをサポート!
- 得意科目と苦手科目を分析した
完全オーダーメイドだから取りこぼしがない!
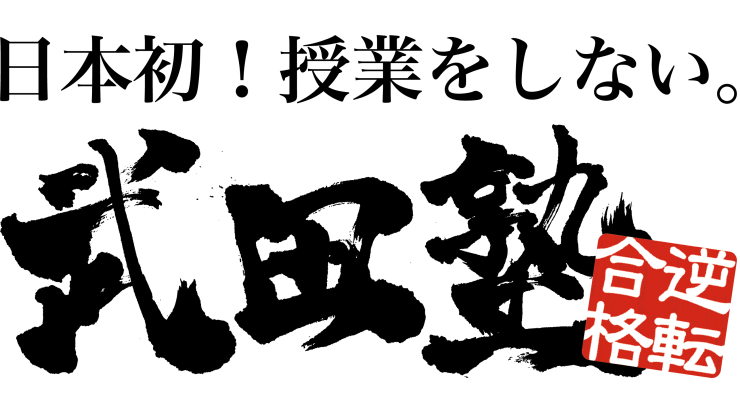
武田塾独自の学習方法で毎年多くの難関大学校合格に導いています。
無料受講相談では、武田塾の学習方法のご紹介から、現在の実力から志望校合格までのカリキュラムを無料でご提案しています。
まずは一度お近くの校舎へご相談ください!
熊本大学医学部はどんなところ?

2019熊本大学医学部の学費・授業料
近畿圏を中心に西日本はその面積に対して医学部の密集度が高い地域であり、特に九州地方は私立大学も含めると人口比で医学部の多いエリアです。
したがって地元での進学を考える受験生にとって選択肢は多くなります。
その中で熊本大学医学部はどのような立ち位置にあるのでしょうか。
熊本大学医学部の入試偏差値や国家試験の成績など、他の大学の医学部と共通する特徴や世間の評判も含めて、細かく分析してみましょう。
入試偏差値は中堅~下位クラス、国家試験成績は振るわず、進級は徐々に厳しく
熊本大学医学部の入試時点偏差値は67.2、と全医学部82校中37位となっています。
この偏差値は地方国立医学部の中では中堅から下位クラスの偏差値です。
県内の進学校を中心に学生が集まる医学部といったイメージでしょうか。
一方、熊本大学医学部の国家試験合格率を見ると90%、全医学部80校中55位となっており、入試偏差値から考えるとそれなりの成績となっていますが、国公立医学部の中では振るわない成績となっています。
このことが影響しているのか、進級判定は徐々に厳しくなっているようです。
熊本大学といえば、進級に関してはかなり緩めの大学でしたが、昨今では、特に低学年での留年者者数が増加しています。
国家試験の成績は進級の厳しさにダイレクトに影響されるため、この辺りの指標も受験校決定の際の参考にすると良いでしょう。
医学部受験を考える時に一番に検討するのは、入試偏差値だと思います。
その次に立地や校風などが続きますが、入学後に気づく重要なポイントは、生活圏の便利さや留年率、国家試験の成績です。
これらの指標は受験生向けに大きく広報されることがない上に、医学部受験生の段階ではそこまで意識が向かないのが現実です。
受験勉強に必死な期間ですから当たり前といえば当たり前なのですが、実態を知らないままに入学して後悔する、という学生は少なくありません。
期待と希望を抱いて入学する人がほとんどであるだけに、その落胆も大きいのが医学部であると言えます。
6年間という短くない時間を後悔して過ごすことのないように、色々な角度から受験校を検討することをお勧めします。
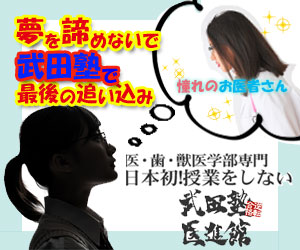
キャンパスは3つ!医学部は2キャンパスを利用
熊本大学には、3つのキャンパスがあり、教養教育を履修する本学キャンパスである黒髪キャンパス、医学部のある本荘キャンパス、薬学部のある大江キャンパスに分かれています。
このうち医学部の学生が利用するのは黒髪キャンパスと本荘キャンパスです。
本学キャンパスと医学部キャンパスは少し離れており、1年次の教養課程の間は2つのキャンパスを行き来することになるため、一人暮らしをする予定の受験生にとっては住む場所に悩まされるかもしれません。
総合大学の医学部の場合、医学部のキャンパスは他の学部と隔離されていることが多く、1年次の間は他学部と同じキャンパスに通い、2年次からは医学部キャンパスのみに通う、というパターンがほとんどです。
そのため、進級する際に引っ越しが必要になることが往往にしてあります。
遠方からの受験の場合、土地勘もなく、どの辺りに住んだらいいのか、生活に便利の良い地域はどのエリアか、といったことはなかなか把握しづらいものです。
しかし、慣れない土地での不要な引っ越しなどでストレスを増やさないためにも、医学部に特有の生活事情については、丁寧に調べておくことが大切です。
在校生の知り合いがいるのであれば、その人にヒアリングするのがベストでしょう。
それが難しければ、受験前に一度、1泊2日程度でいいので泊りがけで大学の周辺を散策してみると良いでしょう。
熊本大学・2つの特徴とは

医学部では、どの大学も同じカリキュラムをこなすことが求められるため、大学独自の科目が設定されることは稀であり、選択できる授業はほとんど無いのが現状です。
また、医学という科学分野の特性上、研究室で扱うテーマも似たものになります。
そのような中でも、大学ごとに目玉となるような特色があり、それによって評判は変わってきます。熊本大学医学部の2つの特徴について見ていきましょう。
特徴1:専門教育は1年次から!詰め込み過ぎないカリキュラム
熊本大学の特徴の1つは、専門教育が1年次から始まるという点です。
多くの総合大学の医学部では、1年次の間はほぼ全てが教養教育で終わり、解剖学や生理学などの基礎医学科目の履修は2年次からスタートというパターンです。
しかし、熊本大学では1年次から解剖学などの講義が始まるため、他の大学よりもゆとりのあるカリキュラム設計となっています。
これは在校生からの評判も良いようです。
医学教育カリキュラムの国際認証を受けるために、日本の多くの医学部がカリキュラムの大幅改訂を行なっており、どの大学でも講義や実習の時間が増えているため、必然的に詰め込み型のカリキュラムになるのですが、熊本大学は上手く分散させたスケジュールとなっているため、学生の負担は少し軽くなっていると思います。
特徴2:柴三郎プログラムで研究医を養成
熊本大学医学部のもう1つの特徴は、「柴三郎プログラム」と呼ばれる研究医養成プログラムです。
このプログラムは3つのステップに分かれています。
高校生からの発掘・育成プログラムである「柴三郎Jr.の発掘プログラム」、学部生のなかから選抜した数名に対して大学院の単位を早期に履修させて研究環境を提供する「プレ柴三郎プログラム」、そして大学院における研究と卒後研修を並行して行う「柴三郎プログラム」の3つです。
3つのタームを用意することで、医学部入学前から基礎医学研究への親しみを育て、卒後も安心して研究できる環境を作っています。
熊本大学医学部で充実した6年間を

熊本大学医学部は、入試偏差値は中堅から下位クラスですが、地元の進学高校の生徒を中心として評判の高い大学です。
また、研修病院が充実しているため、就職先に困ることもありません。
さらに大学独特の研究医養成プログラムなどを設置していることからも分かるように基礎医学の研究に力を入れている大学でもあり、将来設計は考えやすい大学であると言えます。
医学部キャンパスの立地は良く、地方大学ではありますが、6年間という短くない時間を快適に過ごすことが出来る環境です。
勉学に集中して充実した学生生活を送ることが出来る良い大学だと思います。








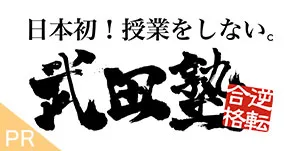
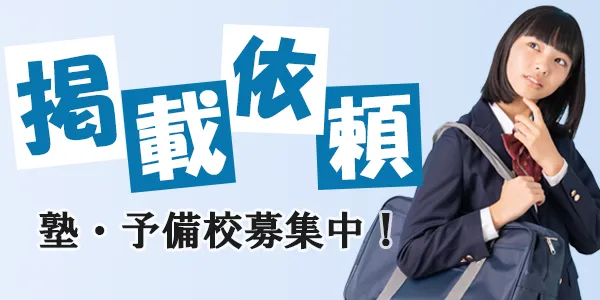
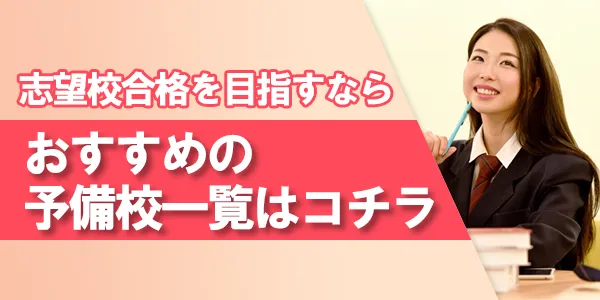


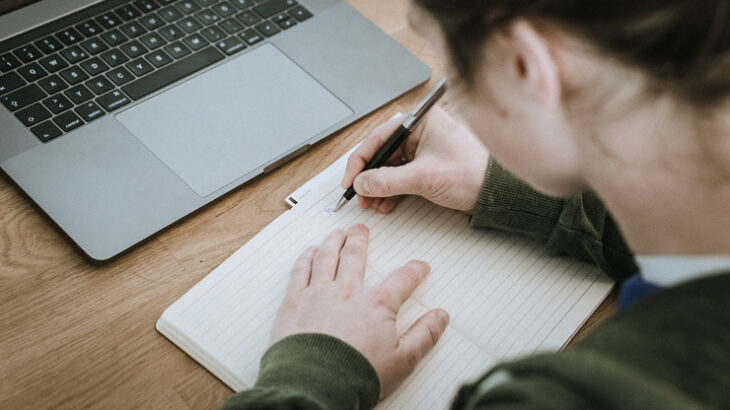



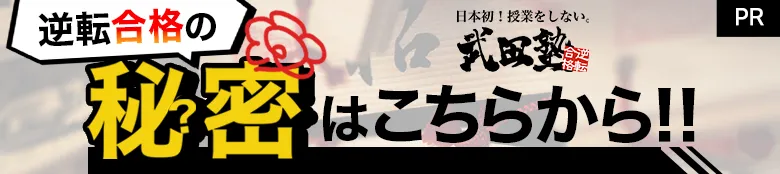
コメントを書く