受験勉強を続けていると、どれだけ勉強しても身についたように感じず不安に思い始める人もいるのではないでしょうか。また、「毎日10時間続けて勉強しているのに模試などの結果に繋がらなかった」といった人もいるかもしれません。
限られた貴重な勉強の時間を、学んだことが全く身につかない無駄な時間にはしたくないですよね。
そこで今回は、確実に学力を伸ばすための効率の良い勉強時間の使い方や、その時間を更によりよいものにするための休憩時の過ごし方について紹介していきます。
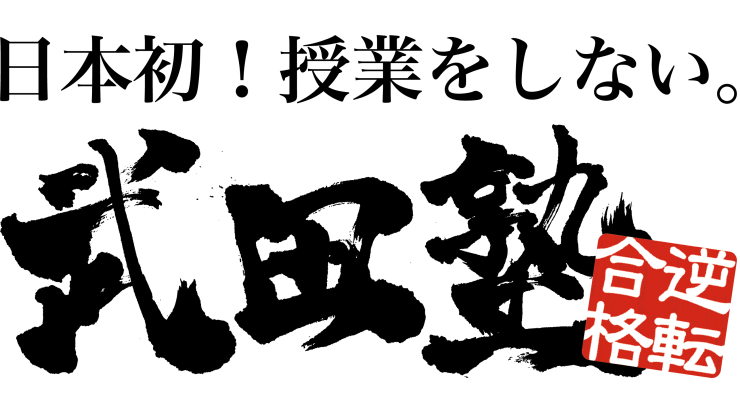
イマからでも間に合う!
難関大学でも武田塾なら逆転合格!
- 授業をしないから『できる』ようになる!
- 自学自習を徹底管理!学習スケジュールをサポート!
- 得意科目と苦手科目を分析した
完全オーダーメイドだから取りこぼしがない!
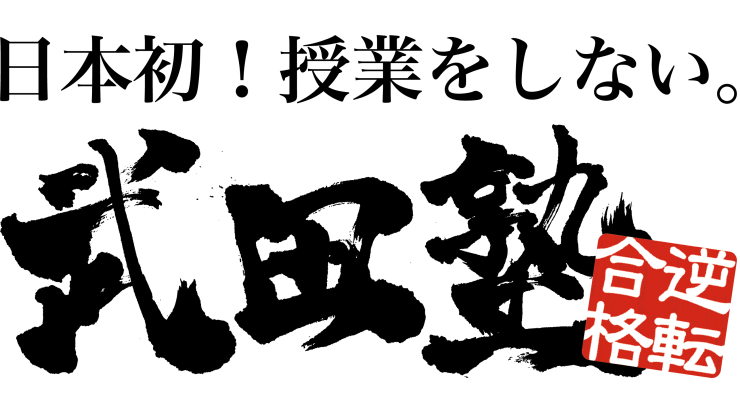
武田塾独自の学習方法で毎年多くの難関大学校合格に導いています。
無料受講相談では、武田塾の学習方法のご紹介から、現在の実力から志望校合格までのカリキュラムを無料でご提案しています。
まずは一度お近くの校舎へご相談ください!
効率の良い勉強時間を探そう

毎日10時間立て続けに勉強しているという人や、途中途中で休憩を挟みながら勉強をしている人など、様々な時間の使い方があると思います。しかし、受験勉強において大事なことは勉強した時間の長さではなく「どれだけ学んだことが身についたか」です。
では、どうしたら自分にとって効率の良い勉強時間を見つけることができるのか。その点についてはじめに紹介していきたいと思います。
集中力が続く時間は人それぞれ
一日に長い時間続けて勉強しても、集中して取り組めていないと学んだことは身につきません。
人が勉強に集中できる時間は、大人で最長90分までといわれています。
ですが中には30分から40分程度しか集中力が続かない、といった人もいるでしょう。
集中力は人それぞれ異なるので、たとえ短いからといって気落ちすることはありません。
効率の良い勉強時間を作り出すため、まずは自分がどれくらいの間集中力を保って勉強していられるかを、実際に時間を計測して把握するようにしましょう。
勉強時間のサイクルを作る
自分の集中力がどれだけ続くか時間を把握したら、それに合わせた勉強時間のサイクルを作っていきましょう。
大事なのは、長い時間続けてやることではありません。自分の集中力が続く時間に合わせて勉強し、途中で10分から20分ほどの短い休憩を挟む。この繰り返しが、効率よい勉強時間にするために大切となります。
例えば、集中力が40分ほど続くという人は、40分勉強をする→10分休むといった形で進めていくようなイメージです。
ポモドーロ・テクニック
自分の集中力がどれだけ続くかいまいち分からない、という人もいるかもしれません。そんな人におすすめなのが、ポモドーロ・テクニックです。
ステップ
この4ステップの繰り返し。これを4回繰り返したら、20分から30分の長い休みを取る。 引用:ポモドーロ・テクニック公式サイト
①勉強したい内容を決める。
②タイマーを25分間にセット
③タイマーが鳴ったら中断。やることシートなどに、やったことをチェックしておく。
④5分休憩。勉強とは関係ないことをして、脳を休める。
ここまで紹介してきたように、効率の良い勉強時間にするために大切なことは短い時間で、休憩を挟みながら勉強をすることです。
短い休憩時間には何をする?
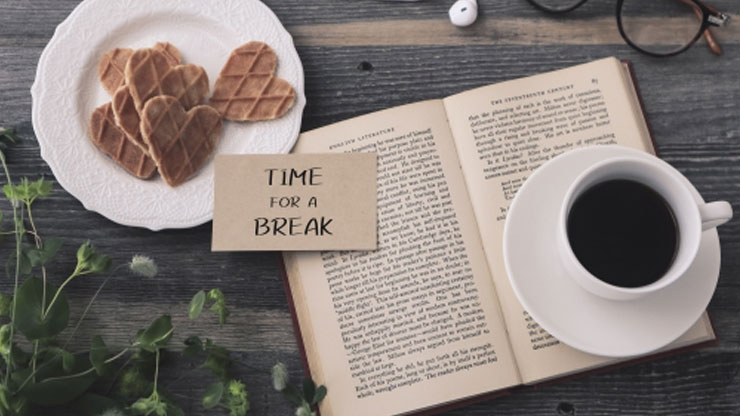
短い勉強時間の合間に挟む、休憩の時間。5分や10分という短い間に、どんな休憩を取ればよいのかあまり思いつかないという人もいるでしょう。
続いて、勉強の時間を邪魔しない休憩の取り方を幾つか紹介していきたいと思います。
糖分を摂取する
頭の働きを良くするためには、ブドウ糖が必要になるといわれています。そのため、ブドウ糖の元になる糖分を摂取することが、効率の良い勉強をするのにあたって重要になります。
糖分を摂るのにおすすめな食材の1つは「チョコ」です。チョコの中でもアーモンドチョコレートやビターチョコレートなどの、脂質を含んでいるものや糖分が控えめのものを食べるようにしましょう。
また、「バナナ」にもさまざまな糖分が含まれていて、休憩中の糖分摂取には効果的だといわれています。
しかし、糖分を摂取し過ぎてしまうとかえって眠くなってしまったりイライラを引き起こしてしまう可能性があるので、摂り過ぎには注意しましょう。
ストレッチをする
凝り固まった体をほぐし血の巡りをよくするために、軽くストレッチをするのもおすすめの休憩方法です。
ストレッチの例(肩ほぐし)
①肩を上までめいいっぱいに持ち上げる。両肩が両耳につくようなイメージでおこなう。
②肩に力を入れ、そのまま3秒キープ
③一気に力を抜き、肩を落とす。
他にも首をぐるぐる回してみるなど、自分の体のどこが疲れているかを意識して、その部位に合ったストレッチをしましょう。
スマホをいじらない
休憩時間は、ついついスマートフォンなどで友達からの連絡を確かめてしまいたくなりますよね。ですが、短い休憩のときはスマートフォンなどを触ることは避けましょう。
中途半端に友達と連絡を取り合うと、その後の返信が気になって集中力が削がれてしまう可能性もあります。また、勉強以外で脳や目を酷使してしまうことになります。
脳や目を休めることを目的とした休憩であることを忘れないようにしましょう。
キリが悪い段階でも躊躇しないで休む
休憩前に起こりがちなのが、休憩時間になったけどもう少しで問題が解き終わるという状況です。この一問を解き終わらせてスッキリした気持ちで休みたい、という風に思ってしまうのも無理はありません。
ですが、それは逆に勉強を再開する気力を奪ってしまうことにも繋がりかねません。
人は、「まだ達成していないものがある方が印象に残る」という心理状態になることが多いとされています。休憩後も勉強を続けるのだという気持ちを保つために、キリが悪いところでも躊躇しないで休むようにしましょう。
より効率の良い勉強時間にするためのコツ
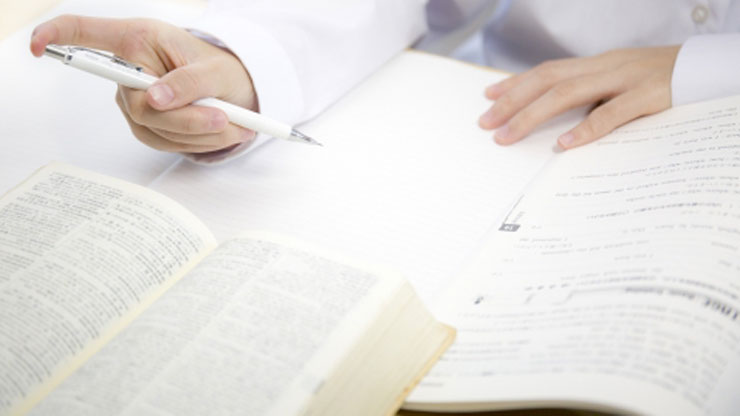
ここまでは、効率の良い勉強時間にするために「どれだけ勉強に集中できる時間を作れるか」を意識することが重要だと紹介してきました。
最後に、より集中力を高めるためのコツを紹介していきます。
勉強に必要ないものを置かない
スマートフォンや漫画、ゲーム機などついつい近くに置いておきたくなってしまうものは多いと思います。
ですが、目に入ったらついつい手を伸ばしてしまうものがある環境は、集中力を妨げてしまいます。机の引き出しや棚にしまうか、どこかに隠しておくようにしましょう。
また、何も物がない場所に移動するのも方法の一つです。
昼寝をする
お昼ご飯を食べ終わった後の深刻な問題のひとつに「睡魔との戦い」があります。
勉強をしていると、ついつい「寝ちゃダメだ」と思いがちですが、その思い込みは逆に眠いという感情を悪化させます。眠くなってしまって、耐え切れないときは潔く寝るようにしましょう。
15分から20分くらいの仮眠が適切とされています。
寝すぎないように、アラームをかけることを忘れないでくださいね。仮眠しても眠いときは、軽く身体を動かしてみましょう。
勉強内容を前もって考えておく
一日の初めに、その日の勉強内容を考えておきましょう。
何も決まっていない状態からダラダラと勉強をするよりも、「今日はこれをやる」と明確に目標を決めておくことで、集中力を高め効率の良い勉強をすることができます
また、午前と午後でやる科目を変えるのもおすすめです。
午前:脳が最も活発に動くため、思考力が問われる数学・現代文・理科などを勉強する。
午後:眠くなりやすい午後は、1回仮眠をとったあと国語の記述問題や英語の長文問題など頭を使う勉強をする。
夜:社会などの暗記科目に時間を費やす。
身につく勉強をするために
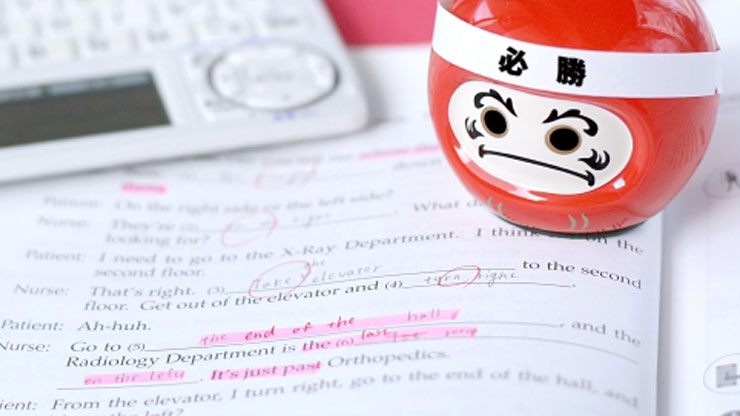
今回は、効率の良い勉強時間を作るために大事なことをいくつか紹介してきましたが、いかがでしたか?
限りある時間の中で、全ての教科を完璧に学習するのは難しいことだと思います。その貴重な時間を無駄にしないためにも、自分の集中力が持続する時間を見極め、効率よい時間で勉強ができるように工夫していきましょう。
そして、効率が良い勉強の時間を見つけたら、次はその勉強時間を十分に活かせる勉強法を身につけていきましょう。
正しい勉強法が分からない人のために、武田塾では無料で相談を受け付けています。今回のコラムを読んでもっと詳しく効率の良い勉強法を知りたいと思った人は、ぜひ活用してみてください。
・『授業をしない』という独自の勉強方法
・参考書を使ったスピード学習
・効率的に短期間で成績をあげる勉強法
・現在の成績から志望校への最短ルート
・奇跡の逆転合格カリキュラム
全国続々開校中の武田塾!!
- 料金はどのくらい?
- 具体的に成績が上がる勉強法って?
- 逆転合格はできるの?
武田塾に関する料金やコース、志望校合格の勉強方法など無料で相談!まずはお問合せ下さい。
無料受験相談はコチラから







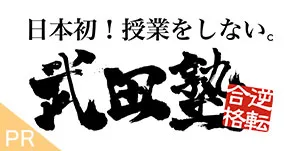
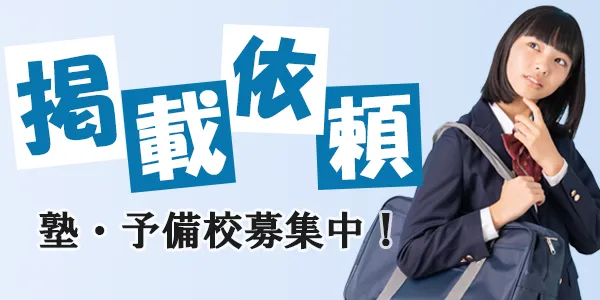
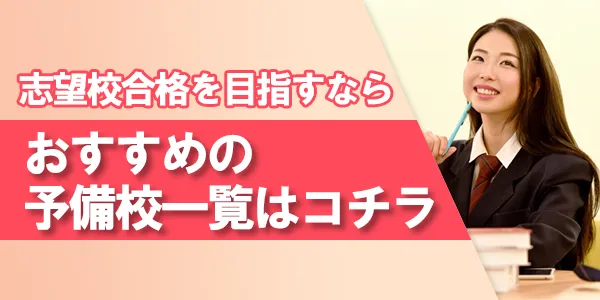
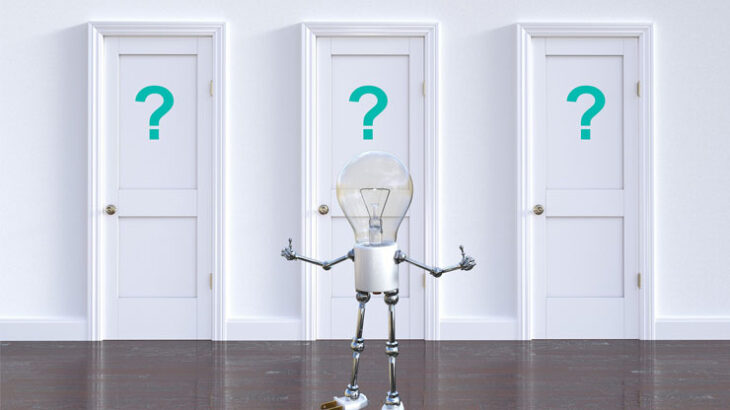

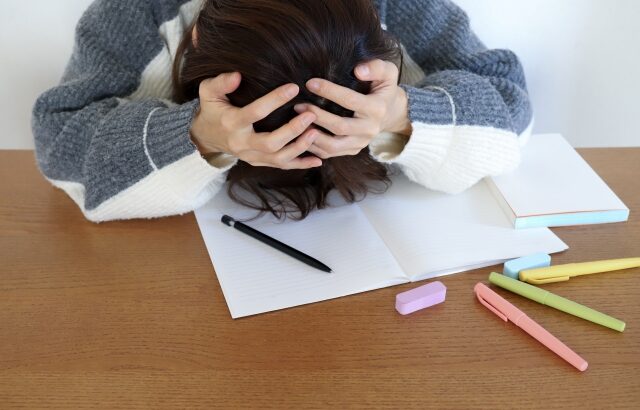


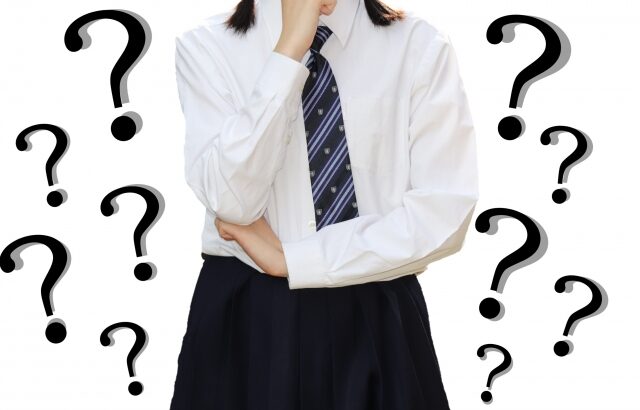
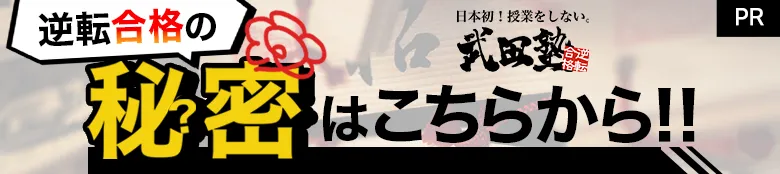
コメントを書く